こんにちは。
このブログは私、明円寺若院橋本ケント(@hashikento99)が住職になるまでに完成を目指して綴っています。
令和三年の節分は2月2日でした。どうやら124年ぶりだそうで日本人全員が初めての節分2月2日を迎えました。
地球が太陽の周りを一周するのに365日とちょっとかかって時間やカレンダーがズレるそうでその調整だとか。そしてそして!!
今回の節分は他にもずいぶんと違うところもあったそうです。
私の母は保育園の園長をしています。園では毎年鬼がきてくれて豆をまくイベントがあるのですが、今回それを終えた後に園長である母がこんなことを教えてくれました。
「今年の節分は異様だった。鬼を倒しにかかる子どもたちが多くて。これは鬼滅の刃の影響だ。攻撃的で暴力的でこれはよくない。私はいのちの大切さを教えたい。何か手はないか?」と。
母の話を聞いて私の第一印象は、「いのちの大切さがわかっているからこそその平穏をおびやかすものに対して果敢に立ち向かう姿はコロナ禍にも頼もしいのでは。」というものでした。
主人公の炭治郎は家族を奪われ仲間を殺され大切ないのちを奪う鬼に立ち向かうのです。しかもただの勧善懲悪ではなく炭治郎はいいます。「鬼は悲しい生き物だよ。」と。
鬼はもともと人間であったという設定です。登場人物はそれぞれの縁の中で、鬼になるか鬼を倒す側になるか本当に紙一重であるとストーリーを知ると感じるところでした。
炭治郎たちは、いのちの大切さを知るからこそ鬼に立ち向っているのです。なので、ひとつの手としてまずは母は鬼滅の刃をちゃんと見て知ってもらおうと思います。(SP版のDVD渡した)
そして、とりあえず園長の想い「いのちの大切さ」というのを鬼を通じて感じてもらうためにはどうすればいいか。私のオススメはこちらです。
地獄の絵本と極楽の絵本
とりあえず園長にこの本を渡しました。
この地獄の絵本むちゃくちゃ怖いんです。大人でもぞくっとします。
地獄絵図はもちろんのこと、文章もめちゃくちゃ怖い構成です。鬼を通じて「いのちの大切さ」を伝えるにはこの「地獄」しかありません笑
ほんと子どもも大人も興味深く見てくれるんですよね。なぜか?やはり、みんなどっかに心当たりがあんでしょう。
「どんなことをしたらどんな地獄にいってどんな鬼にいためつけれるか。そして自分はどこにあてはまるのだろう」
きっとそんな感覚ではないでしょうか。昔の人はそれがものすごくリアルだった。なので地獄に生まれないよう仏を拝んだわけです。
現代の人でも当てはまるところがありぞくっと怖くなるのですが、地獄はもはやリアルではない。とはいえ、現代には現代の表現の仕方があります。それはまた別の投稿で。
この本のミソは、地獄の絵本だけでなく極楽の絵本も一緒に見せるとこです。私は極楽の絵本の方が好きなんです。すごく好きで法事にも使ったります。
当時地獄がリアルな人たちにとっては極楽もリアルでした。これも現代人にとっては以下同文ですが、それなりの表現が必要です
。
一つ言えることは地獄も極楽も、今生きる者の世界の話ってことです。現代人がいま現に実感しているところじゃないでしょうかね、コロナ禍含め。
極楽の絵本で一番ぐっとくる、シーンを紹介して終わります。
「どんなふうでもいいから」とても安心しませんか。地獄の絵本では怖ろしい報いをうけますが、仏と共にある人生では仏さまがご一緒の極楽の世界なのです。
この安心をもっていただくために、極楽の絵本も一緒によんでいただいき恐怖で終わる地獄の絵本のままに終わらさません。こういう風にうちの子どもたちに読ませています。
「いのちの大切さ」これは理屈じゃありません。大人がいのちというものを尊く扱えばこどもたちにおのずと伝わります。
教育上なにかするのであれば、とりあえずこの絵本をおすすめします。と、園長の机に置いてきました。
節分と鬼、これは深いですね。
それでは仏前で会いましょう。
南無阿弥陀仏


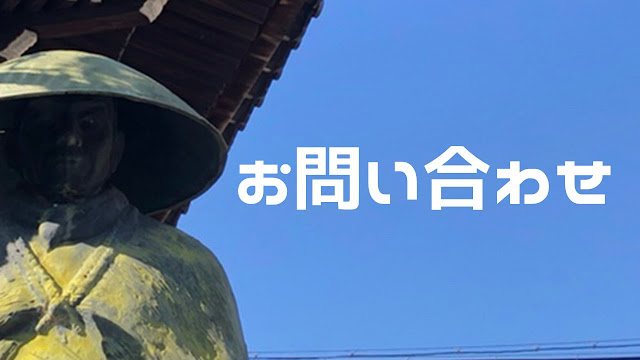

.png)









0 件のコメント:
コメントを投稿